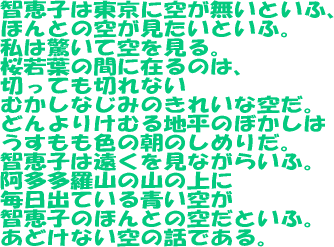�@13:50�A���㒅�B1,700m�B
�@��͖��ŁA�k���͐���Ԃ������Ă���B�u�z���g�E�́v�Ƃ��������Ȃ��]�̌i�F�ƁA�u�l�I�v�Ƃ�����i�F�������ɓW�J���Ă���̂��B


�@�₾�炯�̒��i���������j�ɂ́A���B���ǐ_�Ђ��K�ƎO�p�_���������B
�@�߂��̎R�͖��֎R��S�R���낤���B�͂邩�֒�A��ȁA�����̘A��������B�ꂵ�Ă���悤���B
�@��؈ꑐ���Ȃ������R���ŁA���낲���̑�����C�ɂ��Ȃ���A���炭�݂͂�ȂƂ��ꂼ��̊�т���荇���B����܂Ɋ��������ď��������������Ă����B�^�C�~���O�悭�ē���J����̐������������B
�u���R���܁[���I�v�@14:00�B
�Ό�

�@20���قǃK���������ƉΌ����������B���̏����O���痰���̏L�����Y���Ă���B
�@���m���Ό��͉��F�Ɣ��̂܂���ŁA�������ɂЂƋؓ������オ���Ă���B�w�q�b�q���x�̊��S�Ƃ͎��Ă������ʍr�����钭�߂ł���B���Ȃɂ��N���Ă��s�v�c�łȂ��`�����B
�@�����A3�N�O�i1997�N�j��4�l�ɑ����āA��N�����̗����ЂŖS���Ȃ����o�R�҂�����Ƃ��B�D�����ƗY�X�����̉A�ʼn���ނ����B���ǎR�̎��i�ł������B�@
���R�A��
 �@�o��ł͂Ȃ����C�ɂƂ߂Ȃ��������A�n�C�}�c�I
�@�o��ł͂Ȃ����C�ɂƂ߂Ȃ��������A�n�C�}�c�I
�@����ȕW��(1,700m�A�Ⴂ)������A�\�����ʏo��������B�悭����ƁA���E�͂����Ƃ����Ȃ̂��B
�u���N���ł����A������������ł���v�A�ē���J�������Ă����B�R�͂����ł��A�ߍ��Ȏ��R�̖҈Ђɑς��Â��Ă����ʂ��������B
�@�h�b�B�h�Ƃ������A�b���������p�͔������B������n�C�}�c���\�����Ă���Ƃ���A����痁i�����܁j�����𐒁i�����j�߂邩�̂��Ƃ����R�A�������ȗe�p�ōʂ��Y���Ă����B
�@�h�E�_���c�c�W�����ꂢ�ł���B��i���������j�Ɖ��ƐԂ̉Ԃт炪�̔w�i�ɑN�₩���B
�@��N�Ȃ�A���܂��J�G�f�̍g�t�^������̂悤�Ȃ̂��B���N�͂܂������̒p���炢���x�c�c���̌i�F���̂Ă����̂ł͂Ȃ����B
�@���R�̑���Ɍ��Ƃ�Ă��邤���ɁA���͐Ռ`���Ȃ��Ȃ��Ă����B��͔��_���Ȃт��������B�c�c�D���͕ς��Ȃ��B�@
���ǂ��Ȃ��b
�@�Ό����߂���Ƃ��܂͂Ȃ��݂̓D���ƃK����A�ǂ�����C�������Ȃ��B���ӂ�����������ɂ����B
�@�����B�ꂷ��R���݂̌i�F�����E�̊�������������A���C���U���Ă��܂��B���ׂ���]�т����Ȃ������̂̓��b�L�[�������B
�@�����Ԃ藧��������AJ�������֗U�i�����ȁj���Ă��ꂽ�B�������璭�߂����B���ǂ̘A�R�͈�ې[�������B

�u�E�̂ق�����S�R�A���֎R�A�����ć��������B���ǎR�ł��B���܂܂ł������ɂ����̂ł���B���̉��ɘU�R���X�������܂��ˁv
�@�����_��w�i�ɁA���B���ǂ̘A�R�����ɕ���ł���B�ߌ�3���߂��̌i�F���B
�@���̌��i�A�G�߂����ԑт��Ⴄ���A�w�q�b�q���x�̇����ǂ��Ȃ��b���Ŏ��i�����j�������Y�̎v����`����ɏ\���ł������B